有給休暇は、働く人の権利として付与されますが、2年で時効になってしまうために、未使用の休暇は消滅してしまいます。
ところが、一部の会社では「失効年次有給休暇の積立制度」を導入し、消滅するはずの有給休暇を特別休暇として活用する動きがあります。
今回は、ストック休暇(失効年次有給休暇の積立制度)について解説します。
ストック休暇とは
未使用の有給休暇を消滅させずに、病気療養や育児・介護などの理由で有給休暇の日数を超えて休暇が必要になった際に、過去に取得できなかった有給休暇を活用する制度です。
会社により名称は様々で「積立有給」などと言われることもあります。
有給休暇は2年で消滅
有給休暇は発生の日から2年間で時効により消滅します。(労働基準法第115条)
(しっかりマスター労働基準法 有給休暇編)
万が一の病気など備えて有給休暇の使用を控え、有給休暇の取得促進が進みにくい場合もあると思います。
ストック休暇を導入することで、「いざという時のために…」と有給休暇を使い控えるのではなく、必要な時にしっかり休める環境が整えば安心ですね。
労働基準法では、年次有給休暇の時効は2年とされている。このように失効した年次有給休暇の取り扱いについては、「そのまま消滅している」とする企業が64.2%となっている。
一方、「特別な目的の休暇として積み立てられる」制度を持つ企業も2割強あり、そのうち8割強の企業が、「病気休暇」制度としている。
引用:付与から2年を経過した年次有給休暇の取り扱い
有給休暇 積立制度の仕組み
法定休暇の有給休暇とは異なり、有給休暇積立制度は会社が法定外休暇として制度を設けるため、ルールは会社で独自に定めることができます。
以下のようなルールを設けることが一般的です。
・年間に積立可能な日数、総積立日数の上限
・有効期限、取得単位
・使用目的の制限(病気療養、育児・介護など特定の目的に限り使用できる場合が多い)
失効年次有給休暇の積立制度の規程例
(対象者の範囲を定め、時間単位の取得を可能にしているケース)
第○条
① 前条第○項により翌年度に繰り越された年次有給休暇のうち、当該年度
末までに未使用のために失効する日数(以下「失効年休」)については、
10 日を限度に積立・保存して、次年度以降に取得することができるものと
する。
ただし、既に失効年休を積立・保存している場合は、積立・保存してい
る日数と新たに積立・保存しようとする日数の合計が 20 日を超えない範
囲でのみ積立・保存できる。
② 前項において積立・保存された失効年休は、次のいずれかの事由がある
場合に限り、使用できるものとする。
(1)私傷病
(2)家族の看護・介護
(3)労働者が養育する子の予防接種又は健康診断
(4)労働者が養育する未成年の子の世話
(5)不妊治療
(6)(資格取得や能力向上のための)自己啓発
③ 積立・保存された失効年休を使用しようとする者は、あらかじめ所属長
に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ
届け出ることが困難な場合は、事後速やかに届け出なければならない。
④ 第1項に定める積立・保存できる失効年休の最小単位は0.5日とし、
同失効年休の使用の最小単位は1時間とする。
引用:失効年次有給休暇の積立制度の規程例
ストック休暇導入のQ&A

ストック休暇を導入するメリットは?
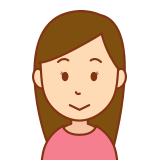
福利厚生の充実がアピールできるので人材確保・定着率の向上につながると思います。

デメリットはあるかい?
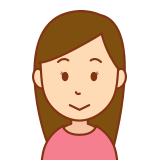
管理の負担やコスト増加といったデメリットもあるので、導入には慎重な検討をお願いします。
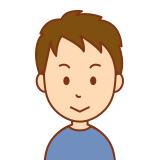
積立できるなら、有給休暇を取らずに貯めておく方が得では?
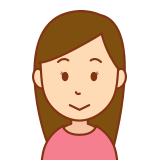
有給休暇を使い休息を取ることで仕事の効率が上がったり、ストレス軽減につながるからずっと使わずに有給休暇を貯めるのはおすすめできないです。
まーちゃんのひとりごと
「積立制度があるから休みを取らなくていい」ではなく、定期的にリフレッシュしながら、将来必要な時のために少しずつ貯めていけるような制度として運用できるのが理想ですね。
【ストック休暇とは】時効になった有給休暇 積立制度について解説!のまとめ
いかがでしたか
この制度をについて詳しく知りたい場合は、病気療養のための休暇 | 働き方・休み方改善ポータルサイト・積立休暇の活用事例をご覧くださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
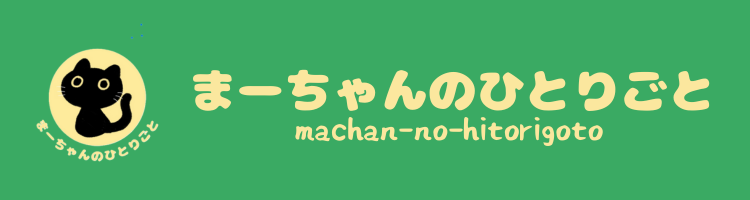
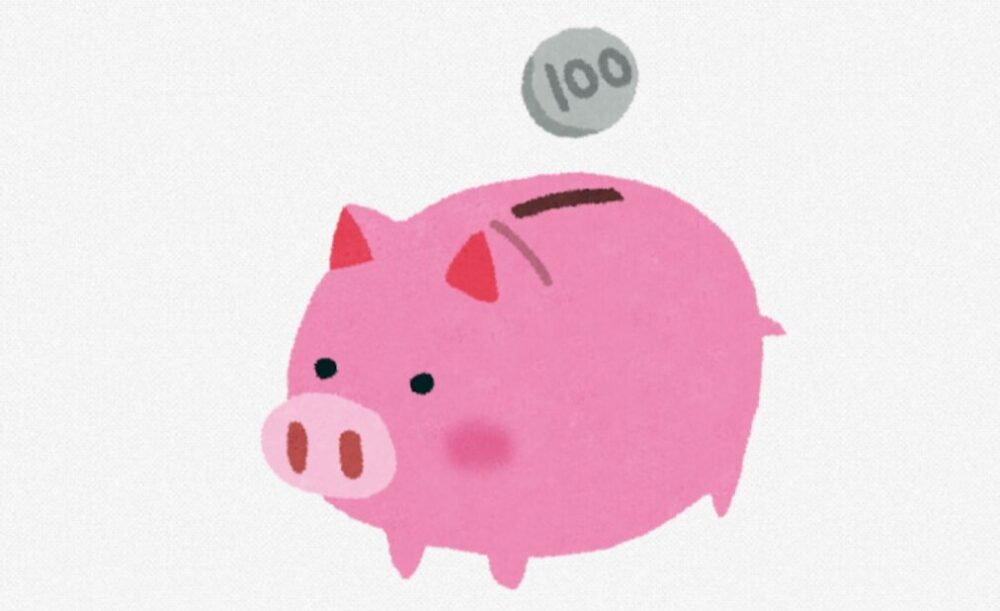



コメント